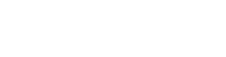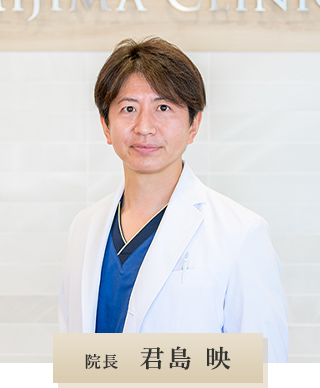過敏性腸症候群
 過敏性腸症候群は、主にストレスが原因となり、腸が慢性的な機能異常を起こしている状態です。潰瘍性大腸炎や大腸がんなどとは異なり、炎症や潰瘍などの器質的な病変は伴わないのですが、下痢や便秘、腹痛、下腹部の張りなどの症状に悩まされます。大腸などは、第二の脳とも言われており緊張、不安、ストレスなどの影響を受けやすい器官だと考えられています。そのため、患者さんが強いストレスを感じると、消化器症状が起こりやすくなるのです。近年では腸脳相関障害とも呼ばれ腸の状態が悪いと脳へ悪影響及ぼし、その脳の不調が再び腸に悪影響を及ぼすと考えられています。逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、下痢型の過敏性腸症候群、若年者の便秘(過敏性腸症候群便秘型を含む)もこの一連の障害と考えられております。精神的なストレスがなかったとしても、疲れがたまっている方、脂っこい料理を食べ過ぎる方、お酒を飲み過ぎる方、生活習慣が不規則な方が過敏性腸症候群になるケースもあります。
過敏性腸症候群は、主にストレスが原因となり、腸が慢性的な機能異常を起こしている状態です。潰瘍性大腸炎や大腸がんなどとは異なり、炎症や潰瘍などの器質的な病変は伴わないのですが、下痢や便秘、腹痛、下腹部の張りなどの症状に悩まされます。大腸などは、第二の脳とも言われており緊張、不安、ストレスなどの影響を受けやすい器官だと考えられています。そのため、患者さんが強いストレスを感じると、消化器症状が起こりやすくなるのです。近年では腸脳相関障害とも呼ばれ腸の状態が悪いと脳へ悪影響及ぼし、その脳の不調が再び腸に悪影響を及ぼすと考えられています。逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、下痢型の過敏性腸症候群、若年者の便秘(過敏性腸症候群便秘型を含む)もこの一連の障害と考えられております。精神的なストレスがなかったとしても、疲れがたまっている方、脂っこい料理を食べ過ぎる方、お酒を飲み過ぎる方、生活習慣が不規則な方が過敏性腸症候群になるケースもあります。
主な症状について
 過敏性腸症候群は、よくみられる症状の違いにより、便秘型、下痢型、混合型に分けられます。このうち便秘型は、腹部の痛みや張りを伴う便秘が特徴的であり、女性に多いタイプだといわれています。下痢型は、文字通り下痢が繰り返されるタイプであり、男性によくみられるといわれています。混合型は、便秘と下痢の両方が繰り返されるタイプです。このほか、3つのどのタイプにも当てはまらない機能異常を起こすケースがあり、分類不能型と診断されます。
過敏性腸症候群は、よくみられる症状の違いにより、便秘型、下痢型、混合型に分けられます。このうち便秘型は、腹部の痛みや張りを伴う便秘が特徴的であり、女性に多いタイプだといわれています。下痢型は、文字通り下痢が繰り返されるタイプであり、男性によくみられるといわれています。混合型は、便秘と下痢の両方が繰り返されるタイプです。このほか、3つのどのタイプにも当てはまらない機能異常を起こすケースがあり、分類不能型と診断されます。
過敏性腸症候群の診断基準(ローマIV基準)
直近3か月のうち、月に4日以上の頻度で腹痛や不快感が繰り返し起きており、以下の3つのうち2つ以上に当てはまる方が該当します。 ・排便によって症状が和らぐ ・症状にあわせて排便の回数が変化する ・症状の出現にともない、便の形状が変わる このような症状がある場合は、IBSだけでなく他の病気の可能性も考慮し、大腸カメラ検査を行って、大腸に異常がないか確認する必要があります。
過敏性腸症候群の検査
 過敏性腸症候群の患者さんは、器質的な病気がみられません。つまり、検査によって過敏性腸症候群を見つけるわけではないのですが、診断をつけるためには、何の病変もないことを確認する必要があります。そのため、大腸カメラ、腹部CT検査、バリウム造影検査などをすることがあります。
過敏性腸症候群の患者さんは、器質的な病気がみられません。つまり、検査によって過敏性腸症候群を見つけるわけではないのですが、診断をつけるためには、何の病変もないことを確認する必要があります。そのため、大腸カメラ、腹部CT検査、バリウム造影検査などをすることがあります。
主な治療について
 治療していく上で、最も大切な事は病状を患者様は充分認識することです。その上で、患者さんが訴えている症状などを考慮して治療方針を決めていきます。基本的な治療としては、腸管運動改善薬、腸内細菌層の異常合併していることが多く整腸剤、便の形状を調整する薬となります。また、例えば、下痢の症状が強いときには、下痢を調整する薬や下痢止めなどを使用していきます。また、便秘の症状が強いときには、便秘の薬も併用いたします。発症の原因がストレスと考えられる場合は、ストレスを緩和させるために抗うつ薬や抗不安薬を使用することも稀にあります。基本的にはこうした薬物療法によって症状を改善させていきますが、さらに生活習慣を見直すための食事療法や運動療法を取り入れることもあります。当院では、治療を行っていく上で、1番初めに病状を理解をしていただくことを重要視しており、診察時に詳細に説明させていただいております。
治療していく上で、最も大切な事は病状を患者様は充分認識することです。その上で、患者さんが訴えている症状などを考慮して治療方針を決めていきます。基本的な治療としては、腸管運動改善薬、腸内細菌層の異常合併していることが多く整腸剤、便の形状を調整する薬となります。また、例えば、下痢の症状が強いときには、下痢を調整する薬や下痢止めなどを使用していきます。また、便秘の症状が強いときには、便秘の薬も併用いたします。発症の原因がストレスと考えられる場合は、ストレスを緩和させるために抗うつ薬や抗不安薬を使用することも稀にあります。基本的にはこうした薬物療法によって症状を改善させていきますが、さらに生活習慣を見直すための食事療法や運動療法を取り入れることもあります。当院では、治療を行っていく上で、1番初めに病状を理解をしていただくことを重要視しており、診察時に詳細に説明させていただいております。